獺祭 ――― 正岡子規の魂が乗り移った日本酒
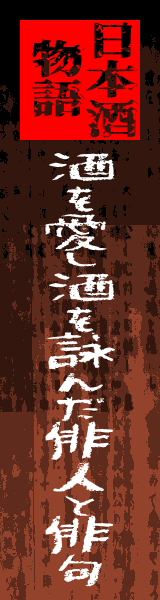 日本を代表するプレミアム日本酒として世界中でその名を轟かせる「獺祭」。その洗練された味わいはもちろんのこと、酒銘に込められた奥深い意味合いにも、実は明治の文豪、正岡子規の影が宿っています。直接的な師弟関係や薫陶があったわけではないものの、時を超えて通じ合う両者の「革新」への情熱が、「獺祭」という酒名に凝縮されているのです。
日本を代表するプレミアム日本酒として世界中でその名を轟かせる「獺祭」。その洗練された味わいはもちろんのこと、酒銘に込められた奥深い意味合いにも、実は明治の文豪、正岡子規の影が宿っています。直接的な師弟関係や薫陶があったわけではないものの、時を超えて通じ合う両者の「革新」への情熱が、「獺祭」という酒名に凝縮されているのです。
「獺祭」という言葉は、中国の故事に由来します。カワウソ(獺)が捕らえた魚を川岸に並べる習性が、まるで神仏に供え物をして祭りをしているように見えることから、「獺祭魚」あるいは「獺祭」と呼ばれるようになりました。そしてこの言葉には転じて、多くの書物や資料を広げ散らしながら詩文を練る様子を指す意味も含まれるようになりました。
正岡子規は、まさにこの「獺祭」の精神を体現した人物でした。彼は自らの俳号の一つを「獺祭書屋主人(だっさいしょおくしゅじん)」と名乗り、膨大な書物を読み込み、資料を渉猟しながら、旧態依然とした俳句の世界に新風を巻き起こしました。既成概念にとらわれず、写実性を重んじ、俳句の革新を志した子規の姿勢は、当時の文学界に大きな衝撃を与えました。彼の代表的な俳論集も『獺祭書屋俳話』と題されています。
一方、山口県岩国市にある旭酒造が「獺祭」という酒を世に送り出したのは1990年のことです。それまでの旭酒造は、地酒として「旭富士」を醸造していましたが、経営状況は芳しくありませんでした。三代目蔵元となった桜井博志氏(現会長)は、逆境の中で「伝統とか手造りという言葉に安住することなく、変革と革新の中からより優れた酒を創り出そう」という強い思いを抱きます。
当時、日本酒業界では「杜氏の勘」に頼る酒造りが主流でしたが、桜井会長は科学的なデータ分析に基づいた酒造りを導入し、それまでの常識を覆す精米歩合2割3分という究極の純米大吟醸を開発します。まさに「他がやらないことをやる」という、子規に通じる革新の精神がここにありました。
この「獺祭」という酒名を選んだ理由について、旭酒造は「弊社の所在地である獺越(おそごえ)の地名から一字をとった」ことに加え、「明治の日本文学に革命を起こしたといわれる正岡子規が自らを獺祭書屋主人と号した事から、この山奥から革新的な酒造りに挑戦する弊社の酒名に『獺祭』と命名した」と説明しています。
つまり、「獺祭」という酒銘には、旭酒造が所在する地の縁に加え、正岡子規が体現した「既成概念にとらわれず、新しいものを創造する」という革新の精神が込められているのです。子規が文学に革命をもたらしたように、旭酒造もまた日本酒の世界に新たな価値観を提示しました。
正岡子規が膨大な知識を収集し、分析することで新たな俳句の世界を切り開いたように、旭酒造もまた、徹底したデータ管理と分析によって、高品質な日本酒を安定して生み出す「杜氏のいない酒蔵」という独自のスタイルを確立しました。この共通する「革新」への情熱こそが、時代を超えて「獺祭」という言葉が持つ意味を深めていると言えるでしょう。
「獺祭」は単なる高級日本酒ではなく、そこには日本の文化と文学、そして絶え間ない挑戦の精神が息づいているのです。正岡子規の「獺祭」にまつわる足跡を知ることで、私たちは一杯の酒に込められた深い物語を感じ取ることができるでしょう。
▶ 酒を愛し酒を詠んだ俳人と俳句
